この記事では実際の認知症ケアの事例をもとに、幻視の症状があり、会話のキャッチボールが難しい認知症の方への支援方法についてわかりやすくご紹介しています。幻視とはどのような症状か、ご利用者と信頼関係を築く関わり方について解説しています。
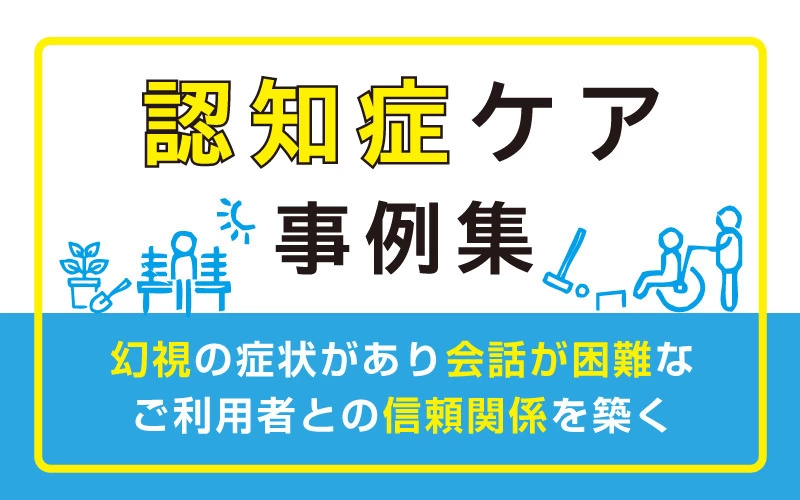
「幻視」という症状をご存じでしょうか。存在していないものが見えることを「幻視」、他の人には聞こえない音が聞こえることを「幻聴」といい、「幻視」と「幻聴」をあわせて「幻覚」といいます。

幻視とは実際には存在していないものが見えるという認知症における周辺症状(BPSD)の一種で、レビー小体型認知症の方によくみられる視覚認知の障害です。見えるものはその方によってさまざまですが、人や動物が多く、亡くなったご家族やご友人が見える場合もあります。
幻視は存在していないものがリアルに見えることが多いです。幻視の症状がある方はそれが幻視だとわかっている場合もあれば、わかっていない場合もあります。
アルツハイマー型認知症でも幻視がみられないわけではありませんが、よく聞くと夢に出てきたなど、明瞭なイメージにみえたわけではなく、むしろ、妄想に分類されるものがほとんどであることに注意ください。
ご利用者に幻視の症状がある場合、その方が見えているものを完全に理解するのは難しく、会話が成り立たない場合も多いかもしれません。その場合どのような関わり方をすればいいのでしょうか。
幻視といえど、その方にとっては実在しているものと同様の「見えているもの」なので、頭ごなしに否定することは避けましょう。
自分が真実だと思っていることを否定されると、その方は「理解されていない」「馬鹿にされている」など、周囲への不信感を強めてしまいます。その方の感じている不安にフォーカスし、その不安を解消するようなケアを心がけましょう。
幻視は暗い場所で起こるケースが多いです。照明を増やしお部屋を明るくしたり、見通しをよくしたりと環境整備で軽減を図ってみましょう。
また、その方の昔から長年使っているものを配置するなど安心できる環境づくりもおすすめです。
今回ご紹介するのはベネッセスタイルケアの認知症ケアから生まれたその方らしさに深く寄りそう40の手掛かり「あなたと生きる世界をつくることば」をケアに取り入れた事例です。
「あなたと生きる世界をつくることば」は、300を超えるベネッセスタイルケアのホームの認知症の方をはじめとするさまざまなご入居者にうまく寄りそえた事例を集めて比較・分析し、再現性を生むためにパターン・ランゲージ※の手法を用いて言語化したもので、ベネッセスタイルケアの社内で活用されています。
※1970年代に、都市計画・建築家のクリストファー・アレグザンダー氏が提唱した、建築・都市計画法において真の住民参加を実現するための共通言語を構築・活用する理論。
リンク認知症ケア実践から生まれたその方らしさに深く寄りそう40の手掛かり「あなたと生きる世界をつくることば」|ベネッセスタイルケア
今回ご紹介するのは、ベネッセスタイルケアの有料老人ホームに入居されたB様の事例です。幻視が見え、介護サービスを拒まれることが多かったB様との関わり方を工夫することで、信頼関係を築きました。
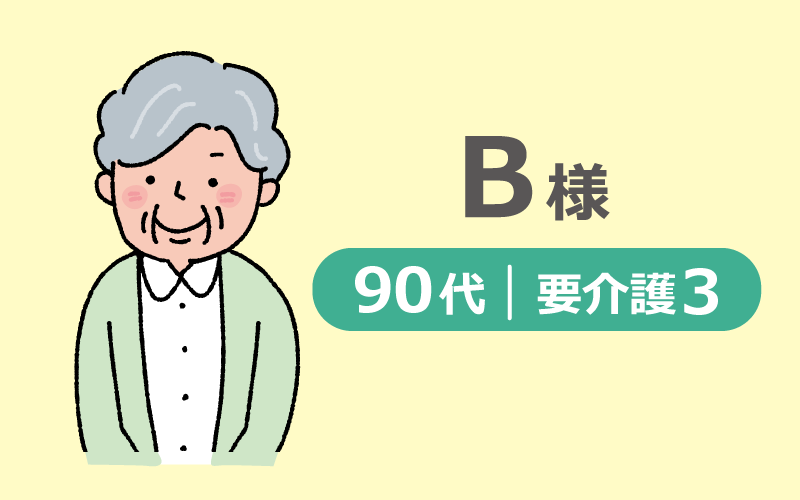
B様 90代 要介護3
入居時に伺ったB様のご希望は「穏やかに過ごしたい」というもので、それを叶えるためにケアを通じて何ができるかを考え、下記の取り組みを実施しました。
B様は、幻視で見えている人との会話に集中されていて、その際は職員やほかのご入居者と会話することは難しいご様子でした。一方、幻視の症状がなく落ち着いていることが多いモーニングケアの際に重点的にお声がけや会話を増やしていくことにしました。
5分お話をしてみてお話ししていただけなければ、時間をおいてから話しかける、別の職員に交代する、ご本人の世界の中での登場人物になりきってお話しする、などさまざまな工夫を重ねていきました。
B様からお声がけいただいたり、ケアのあとに「ありがとう」という言葉が出る、または表情が明るいときなど、B様の気分が良いときに話しかけると、「わかってくれる人」「安心できる人」として認識していただけるらしいということもわかってきました。そのようなタイミングでお食事にお誘いすると、快く応じていただけました。
お手洗いをはじめとするさまざまなお手伝いも、ご本人のタイミングと合っていると応じていただけました。
お食事へのお声がけの際は、大事にされているぬいぐるみと口紅、手鏡の「3点セット」を用意することにし、ご本人のこだわりを尊重しました。

約4ヶ月の取り組みの結果、B様に下記のような変化が見えるようになってきました。
お声がけを継続しているうちに、だんだん会話できることが多くなっていきました。B様がどんなお気持ちでいるのか、どんなことをやりたいのかなどのB様の「らしさ」への理解も深まりました。また、会話の中で排泄ケアをしてほしいといった意思表示をされることも増えました。
以前は、入浴を拒まれることが多く、月1回入れれば良いほうでしたが、取り組み後は月3回程度に入浴回数が増えました。また、入浴のお手伝いをできるスタッフも増えてきました。
久々にお風呂に入られた日はご機嫌も良く、その翌日も職員に「昨日お風呂に入ったの」とお話しされるなど、ご本人にとっても嬉しいことだった様子も伺えました。
また、今までずっと拒まれていた健康診断が数年ぶりに実現しました。
以前はお部屋にいらっしゃることが多く、お食事やおやつもお部屋で召し上がっていましたが、最近ではダイニングやコミュニティルームにいらっしゃることも多くなりました。
また、これまで参加されていなかったレクリエーションに参加されるようになりました。(母の日のフルーツサンド作りや写真撮影イベント、音楽療法など)さらに次第に笑顔が見られるようになり、その変化はご家族が驚かれるほどでした。
今回ご紹介した事例では、お声がけを根気強く行うことでその方への理解を深め、会話の中で得たB様の「その方らしさ」をケアに取り入れた結果、信頼関係を築くことができ、ケアをお任せいただけるようになりました。
また、お声がけの際の声色も明るく元気なトーンではなく、落ち着いた低めのトーンのほうがB様にとっては心地よいのか、話を聞いていただけることが多く、お一人おひとりにあったお声がけの仕方があるのだと、取り組みの中で職員の気づきも多かったそうです。
認知症ケアでは、その方を理解することを諦めずにさまざまな手法でのコミュニケーションを試みることが重要です。ぜひ、この記事を参考に、ご利用者へのケアに取り組んでみましょう。

秋下 雅弘Masahiro Akishita
プロフィール
東京都健康長寿医療センター センター長。1960年鳥取県生まれ。1985年東京大学医学部卒業。東京大学医学部老年病学教室助手、ハーバード大学研究員、杏林大学医学部助教授、東京大学大学院医学系研究科准教授・同教授などを経て、現職。日本老年医学会理事、日本老年薬学会代表理事、日本認知症学会代議員など学会役員多数。専門は老年医学、特に高齢者の薬物使用、老年病の性差。

介護アンテナ編集部Kaigo Antenna Editorial Department
プロフィール
株式会社ベネッセスタイルケア運営の介護アンテナ。編集部では、ベネッセの25年以上にわたる介護のノウハウをはじめ、日々介護の現場で活躍している介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの高齢者支援のスペシャリストたちの実践知や日々のお仕事に役立つ情報をお届けします!
いいねするには
ログインが必要です
ブックマークするには
ログインが必要です
ブックマークするには
ログインが必要です